
 |
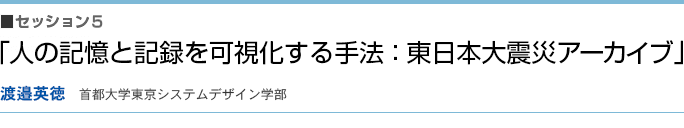
|
本題に入る前に、2011年に作った広島の原爆投下についてのアーカイブ「ヒロシマアーカイブ」の話からスタート。被爆者の証言や、投下された8月6日にいた場所、写真資料などを、グーグルアースを使って今の広島の街に当時の広島の街をよみがえらせる作業を行ってきたという渡邉氏。高校生がインタビュアーになることで、多くを語りたがらない被爆者の心を柔らかく紐解き貴重な証言を引き出した。多くの若者が未来に記憶をつむぎたいと思っているからできたアーカイブだとも。岡本太郎の『明日の神話』という絵画は、ビキニ環礁で被爆した第五福竜丸をモチーフにしている。岡本太郎美術館に「この絵は、地球上のどこの場所に掲示するのがよいか」と尋ねたら、ビキニ環礁を見通す方向に、とのこと。真ん中の怪物は水爆を、右下に第五福竜丸が描かれている。この絵の文脈をよりよく表現する手法の一つになると考えている。東日本大震災アーカイブも同じ仕組みを用いて制作した。
「グーグルアースという現時点で一番使いやすいソフトで作った。広島の場合は、現在から当時への時間軸をさかのぼっていく形で。東日本大震災は、これから復興を果たしていく未来の記録がアーカイブされていく。散在したデータを人の力で集めて一元化し、インターネットで公開する。10年後20年後、高校生が社会にでて大人になったとき、そのときの最新の技術で作ってくれるかもしれない。トップダウンで報道するマスメディアの視点と、いろんな人がボトムアップで提供する災害状況を重ねるという試みが、実際に運用できるようになったら次なる災害の備えになると考えている」
|
 |
 |
|


 |
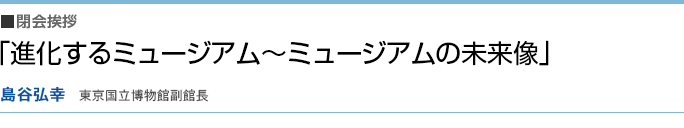
|
冒頭で本田代表理事からあったこの機構の2つの活動目的、すなわち、デジタル文化財の保存と活用、その融合であらたな価値を見つけること。このことはデジタルに限らず、有形の文化財でも全く同じことである、と語る島谷氏。神宮の采野氏は、作成する立場から文化財をどう活用するかを、美術院の木下氏は、修理をする立場から文化財をどう活用するかを、荒俣氏は研究することにどう活かすか、武蔵野美大の寺山氏は創造にどう活かしていくかを、平等院の神居住職は信仰ということをくるめて文化財をどう保存活用していくかを、九州装飾古墳の話では研究と展示ということにつなげる活用の場ということを、渡邉氏は生きたアーカイブをどう活かせるかを、それぞれが自分と複雑に関係があるテーマばかりだと、シンポジウム全体を振り返る。
「文化財というのは残そうという意志があるものでないと残っていかない。中国や韓国は国策で文化情報を発信している。特に韓国は海外に90箇所ほど拠点をつくっている。日本も単発ではなく継続的にそのような取り組みを行う必要がある。世界に点在している日本の文化財もアーカイブしていく必要がある。2020年はスポーツだけでなく文化の祭典でもあると思う。みなさんいっしょになって日本の本当の力と姿を伝えていければと思っている」
|
 |
 |
|


 |
|

 |
会場では以下の展示物による実演なども行われた。
|
 |
●平等院雲中供養菩薩像彩色復元映像
●情報通信でつなぐ祈りの場
●宇治平等院再現映像
●新『文化財 多次元的描画システム』
●『平等院 国宝 仏後壁』偏光カラー画像による国宝絵画
●東大寺法華堂復元映像
●MAU M&L 博物図譜(システム名称 高解像度画像閲覧タッチパネルシステム)
●唐招提寺『鑑真和上坐像』お身代わり造立に際したさまざまな試み
●東日本大震災アーカイブ / アチェ津波アーカイブ
●V×Rダイナソー
●トッパンVR 現代に蘇った『古代青銅鏡』
●ViewPaint Vol.1 フェルメール《牛乳を注ぐ女》
●屋外文化財バーチャル体験システム
●デジタルアーカイブとその可視化の事例
|
 |
|

 |
|
|
|






