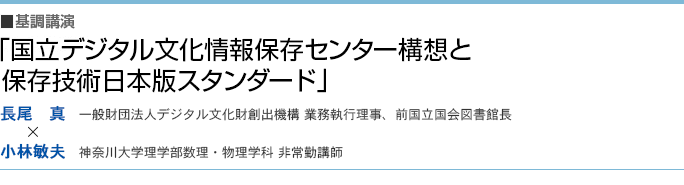
|
長尾 真:
国立のデジタル文化情報保存センターが必要であるという話を中心に話が展開。国宝以外にも地域の郷土資料など十分に保管されているかどうか疑問であり、所在情報は大きな問題であるという。東日本大震災では多くの貴重な資料が失われたが、消失したものを発見して復元しようとしても、そもそもどこに何があったかがわからない。デジタルによる保存復元に焦点をあてる必要がある。個人が所蔵している資料は、オープンにすると子供に引き継ぐとき遺産相続で税金がかかるなど、日本の文化資産は表に出てこない側面もあるので、税制上の問題も含めて考えていく必要がある。京都ではメセナや独自資金で寺や博物館が独自の努力でやっているが、資金面では限界がある。また、デジタル化しても100年200年に渡って保存できるかというと疑問と述べる。
「デジタル化のフォーマットは技術進歩によって変わっていくため、国立でセンターをつくることが必要。京都や仙台はじめ全国的に複数箇所を運用していく。デジタルデータの恒久的な保管運用、事業創出、人材育成、地域との相互連携、権利管理の問題、普及啓蒙の問題、などなど、広い範囲で考える必要がある。優先順位を検討することも大事。小坂先生が会長の議連、国会図書館、文化庁とも連携し、将来に向けて進めたい。2020年の東京五輪は良い機会。日本の文化資産を誰でも見られる、スポーツの祭典であり、文化の祭典でもあるというのが願いである」
|
 |
 |
|
 |
 |
小林敏夫:
誰もが情報端末で全世界の人と通信可能な高度な情報社会がなぜ到来したか、という問いかけから話がスタート。その根底にあるのは半導体の進歩。1つのチップに集積されるトランジスタの数と性能は飛躍的に拡大したが、価格はほとんど変化してないので、情報の処理コストは100億分の1くらいに。これが高度な情報処理ができる世界をもたらし、デジタルコンテンツの爆発的な増大をもたらした。現状の長期保管の戦略は、メモリ技術がシステム寿命と同じなので、ある一定の期間でシステムごと次のシステムに移し変えるというマイグレーションの手法が一般的。しかし継続的に移行するには財政的な問題がある。また、社会的混乱、戦争、大震災、あるいは経済的危機破綻、人為的ミスなどによって途絶えてしまうと残すべきデータはすべて消失してしまう。マイグレーションという戦略は脆弱かつ高コスト。この問題に警鐘をならしている一人が青柳文化庁長官。エジプト文明ではヒログリフという文字を石という堅牢な媒体に刻印してきたため多くの情報が残っている。問題は、この情報はロゼッタストーンが現れるまでは解読できなかったということで、これは示唆にとんだ話だ。もし長期に堅牢に保管できる媒体が存在したとしてもそれだけでは不十分で、いつの時代にもその情報を取り出し、意味を理解できる仕組みが作れることが重要。しかもそれが簡単に安くつくれないといけない、と小林氏は強調する。
「長期に保管できる物理原理が必要なことと、その原理が発現する構造体が壊れないこと。大出力のレーザーで石英ガラスに傷をつけて書き込んでいくという方法や、半導体メモリに可能性があると思っている。半導体メモリの基本構造はシリコン樹脂、石英、セラミックスといった堅牢な材料からできていて耐熱性もあるので実現できる見通しもある。しかしもう一つの用件である、いつの時代にも意味が理解できる仕組みについては検討が必要。メタデータを長期に渡って共通的にその時代時代で管理して、継承していくような仕組み装置をまずつくることが必要。イノベーションを起こすには各分野の研究者・技術者の協力も必要。ただし現在は、上位と下位のレイヤーで認識にギャップがあると感じる。階層間の認識を埋める体制づくりが急務である」
|
|


 |
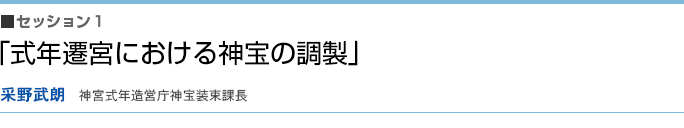 |
昨年2013年10月に、20年に一度の式年遷宮が執り行われた伊勢神宮。第一回目は690年に開催され、以降1300年に渡って続けられ、昨年が第62回目。この式年遷宮の総監督の役割を果たしたという采野氏。伊勢神宮の参拝者は昨年1000万人を突破。神宝ができあがるまでの過程を実物展示とCG映像でも見られる「せんぐう館」も開設し、さまざまな工夫をされるなど新しい試みをはじめている。現在、約7割が終了したという今回の遷宮。御装束神宝の調製について、技術的な話を中心に丁寧にその行いの一つ一つを語る采野氏。遷宮は、社殿のご造営、御殿の中に収める御装束神宝、遷御の儀(祭典)の3つが柱。神宮の御装束の仕様は、927年の延喜式にその骨格がある。その仕様が今でも20年毎の式年遷宮で厳守されている。単に伝承すればそれですむということではある。しかし、人材、そしてとりまく環境が大変大きく20年ごとに変化している。制作図面は1000枚、すべて20年ごとに書き改めていく、と采野氏は語る。
「現図面は昭和初期に制定された図面なので、保管そのものが大変困難。そういった意味も含め、新しい技術を使うということで、今回はデジタル化して保存した。時代の力をうまく使いながら、伝統の技術を次に移行していくということは我々の仕事において大変重要なこと。あたらしい挑戦の意識がないと、前回を越える技術は生まれてこないし、20年ごとの遷宮を滞りなく終えることはできない」
|
 |
 |
|


 |
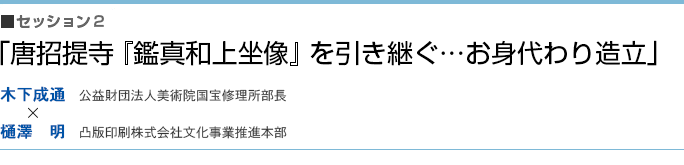
|
 |
 |
樋澤 明:
唐招提寺は、688年に中国の揚州で生まれ753年に来日を果たされた鑑真大和尚によって759年に創建され、763年に弟子の忍基(にんき)が講堂の梁が折れ崩れるという夢をみて、急いでお像を作ったといわれる話からスタート。昨年2013年に、鑑真和上坐像のお身代わり像を、2年以上にわたって当時の技法を解明しつつ美術院が制作。美術院は明治31年に岡倉天津が創建した日本美術院が起源で、国宝などの仏像の修理を手がけている。
「今回の鑑真和上模造制作では、美術院の技術や知見に加えて、凸版印刷が提供した鑑真和上像の3次元立体形状データを加味していただきながら、さらに顕微鏡写真や特殊な光の照射をすることで、新しい科学的なデータも活用されたとのこと。科学の目と、木下さんの鍛えられた技の融合。当時、作者がどういう思いでつくったか。計測したデータの白い粘土細工の指の跡をみて、たぶんこうだったんだろうと意を強くされたという。そんな使い方がデジタルデータにあったということは驚きだった。伝統的な技法や、その中で新しい発見があるということを、私たちも知らなければならないとつくづく感じた。」
|
|
木下成通:
美術院は100年の歴史があり、ずっと現場でやってきたという木下氏。必要なのは自分の手と目と耳と鼻という五感が大事でそれを財産としてやってきた。10年前くらいからデジタルが少しずつ入ってきており、それはとても便利。自分たちの積み重ねた技術とどのように融合するのかはみなさんといっしょに考えていくべきテーマだと語る。鑑真和上像は脱活乾湿という技法で、十代弟子、八部衆、阿修羅などが有名。等身大以上のものはどれも内部に心木がしっかりあるが、鑑真和上は様相が違っている。
「凸版印刷による計測画像をみると表面が凸凹しており、脱活乾湿の特徴である表面の平滑さがなく、粘土を指でトントンとおいていったようなところがあり、そして何より心木がない。これは像造技法では想像できなかったこと。表面が粘土の段階で原型がほぼ出来上がっているということも不思議である。表面にある漆のモデリングは一切ないに等しい。彩色の基本色は凸版印刷の高精細デジタル画像を参考にした」
|
 |
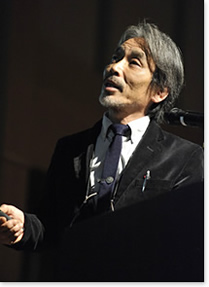 |
|


 |






