〈前ページからの続き〉

吉見(東京大学大学院情報学環)
戦略委員会で最初に議論していたのは、ムーブメントを起こそうということである。

村井(プランニング・ラボ)
箱ものではなく、地域からはじまってクラウドができることをイメージしていた。100人委員会で仕掛けていくことも必要。

小出(公益財団法人渋沢栄一記念財団)
例えば、「このコンテンツをどう作っていったらよいか?」と悩んだとき、良い事例を探すのが大変。デジタル化していくときのノウハウがどこにあるのか。潮流は?そういうことが知れるコンサルタント、知識センターがあると、具体的に進んでいくのでは。

|
 |
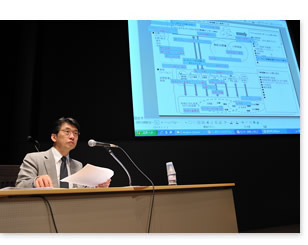 |
|
島谷(東京国立博物館)
東博でも平成の棚卸しをしている。100万点を越えそうだ。映像から考古品まで、一つのフィールドに集めるのには困難を伴う。東博はかなりの蓄積があるので協力できる。活用者のメリットについては、作品あってのデータベースが根底にある。一つに集めるのがなかなかうまくいかない。小さいところはデータを提供することのメリットを認めない。データを提供するメリットを明確にしないといけない。個人情報が含まれているデータも多い。できるところからやっていく必要がある。

小野(株式会社サペレ)
NTT時代に思ったことだが、メタデータといえばダブリンコアというが、決めるまで難航したものである。分類はないよりましと考え、不足があれば拡張したほうがよい。

川口(国立西洋美術館)
利用者のメリットの議論に、一般向けだけでなく、専門家も必要としている。広げて考えていただきたい。

後藤(花園大学)
白地図に「発信」がない。積極的な発信、セールスマンという言葉が出たが、ツイッター、フェイスブックなどを活用した発信が必要では。現場でも、文理のひらきが大きい。カリキュラムをどう考えていくか。入試まで踏み込まざるをえないかもしれない。

石田(東京大学大学院情報学環)
学問としてのかたちを打ち出すこと、やろうとしていることの輪郭が示されないといけない。基礎的な学問の中に位置づけられることが必要だろう。

八村(立命館大学)
政策提言は、提言だけなのか、予算化の資金要求なのか?箱ものの要求と聞こえないように、ヒューマンネットワークを作っていくアプローチのほうが戦略として正しいのでは?

|
吉見(東京大学大学院情報学環)
本田代表理事、青柳業務執行理事にご回答をお願いしたい。

本田(デジタル文化財創出機構 代表理事)
ある段階で予算化の申請をしていきたいという思いである。箱物にしてはいけないという共通認識はある。

青柳(デジタル文化財創出機構 業務執行理事)
きちんとした組織化をする中で、予算要求が必要になることもある。グローバル化の中で、情報化が遅れており、弱体化につながっている。シビルインテリジェントの強化として役立つはずだ。シンボル的なものとして、モラルをつくっていくための組織を定着させることが運動体の旗印になるのではないか。

|
 |
 |
|
柳(国立国会図書館)
MALUIにわざわざ「I(産業)」を入れた。企業の社会的貢献も大事だが、産業としてうまく成り立っていかないとうまくいかない。千代田図書館では、そういう仕組みができるとよいと考えて、六本木ヒルズ内の六本木ライブラリーを参考にした。ある程度商売になっていると聞く。森ビルの中にあるものだが、公共図書館と思っている。MLAも商売になるようにしていくことも必要。中国、韓国に比べて国の予算が少ないことも確か。きちんと要求する必要がある。

礒井(まち塾@まちライブラリー)
戦略の図を逆転するとコンテクストが変わってくる。あえて逆転して、アーカイブ化していく人材育成を考えると、どうなるか。ロジスティクスの部分では、一般の人が素材を上げれば、アーカイブは一般の人が担当できるようになる。センターは箱ものではないという話となると、何に投資するか考えなければならない。YouTube、Facebookに拮抗するエンジンが必要になる。最後には、ナショナルがとれてしまうのでは?逆転すると全部のコンテクストが変わる。

吉見(東京大学大学院情報学環)
さまざまな意見が出てまとめるのも難しいが、戦略委員会からコメントをいただきたい。

南(神奈川大学)
MLA+Uの「U」の重要性。集積の場でもあり、教育の場でもある。若者の場になりすぎている。大学の門戸を開くことで変化していく。

村井(プランニング・ラボ)
コミュニティの「C」も大切。市民の参加が当たり前という体制づくりをしていきたい。

藤原(総務省総合通信基盤局)
地方自治の立場から発言したいが、楽しみを共有してもらい地域住民に返していくことが重要。標準化することは地域ではできない。集約する場で議論していただきたい。

伊藤(鹿島建設株式会社)
建設業としては、箱ものは必要ないとばかり言われるとつらいが、事業化することが課題。海外の人が楽しめるよう、海外にも拠点を作ることもよいのではないか。

吉見(東京大学大学院情報学環)
今日の場もすでに、アーカイブセンターの一つの役割を果たしている。これだけのアイデアが出ている。恒常的に議論していく場を作ろうとすると、なかなか難しい。恒常的にしていくための、深めるための制度、組織をつくるプロセスとして理解していただきたい。これからも継続して注目していただきたい。
|
| 〈了〉 |






